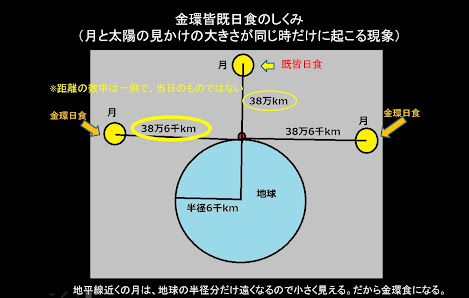2023年7月12日開催の星空案内人勉強会は、テーマは「2023年夏の星空案内のポイント」でした。前半はテーマに沿った話、後半は各自で天体望遠鏡の操作練習をしました。望遠鏡の操作練習の時間を取るため、話は必要なものだけにまとめました。資料は以下のとおりです。 なお、スターウィークの2023年分の資料は、この記事をアップする時点では、スターウィーク事務局の方でまだ更新されていません。2022年版とは満月新月等、月の暦が違いますが、そこだけ注意すればそのまま使えると思います。2023年版は近日中に更新されると思うので(確認は取っていませんが)、急いでなければ更新を待つのがいいでしょう。一番下のリンクはこの記事からはたどれないので、必要な方は各自で検索してください。「スターウィーク 資料」で見つかると思います。 2023年夏の星空案内のポイント 星空案内人勉強会資料 2023.07.12 夏は星に興味を持つ人が増える季節です。新暦旧暦七夕、ペルセウス座流星群、スターウィーク等星に関するイベントが多い上に、夏休みなのでキャンプで天の川を初めて見る人もいるでしょう。 夏の星空を案内する時のポイントを下にまとめてみました。特に一番下の「スターウィーク」の資料は誰でもダウンロードして使えるので、お勧めです。 ※スターウィークとは、「星空に親しむ週間」のこと。毎年8月1日~7日の1週間です。 1. 夏の星空は「夏の大三角」、「さそり座」、「北斗七星から北極星」を案内する 肉眼で見える星(一等星)を教えて星座をたどる。星座を探すには一等星を見つけ、そ の周りの星を つなげて星座を作る。 市街地では三等星まで見えないかもしれないので、「この星座はだいたいこのあたり」 でいい。完全に形を結ぶのは無理でも、一等星を目印に覚えてもらう。 2.見える惑星は「 7月中旬までの金星」と「8月末からの土星 」、「8月前半西の低空の水星」 「遠くて小さくて西に低い火星」。惑星は不作の夏。火星と水星は肉眼では見えにくい ※ 金星 は7月25日には日没時の高度が約15度(ぎりぎり)30日には約9度(もう無...